医療×AIセミナーシリーズ第10回:循環器とAI
-
日程:2019年11月30日(土)
-
時間:15:00-17:00, 17:00-18:00(交流会)
-
会場:東京大学伊藤国際学術研究センター中教室
-
主催:
東京大学未来ビジョン研究センター、慶應義塾大学メディカルAIセンター、エムスリー株式会社m3.com編集部
-
協力:
日本ディープラーニング協会(JDLA)、世界経済フォーラム第四次産業革命日本センター(C4IRJ)
-
対象:
医師ら医療従事者、開発者、政策関与者、医療機器関係者等
-
15:00-15:05オープニング
-
15:05-15:35小川晋平氏講演
-
15:35-16:05小寺聡氏講演
-
16:05-16:55質疑応答・ディスカッション
-
16:55-17:00クロージング
-
17:00-18:00交流会
医療現場での課題解決に向け様々なテクノロジーが導入される中、AIやITの臨床現場での実装も進みつつあります。現場での課題を熟知する医師による開発や実装、医師と協働する開発者ら、社会実装に向けた仕組みをつくる政策関与者も増えてきました。
本セミナーシリーズは、こうした医師や開発者、政策関与者らが、それぞれの経験や知見を基に、開発・臨床現場で役立つ情報を共有し、関係者同士の交流をはかることで、医療現場での新しいテクノロジーの実装を進めていくことを目的として行います。東京大学未来ビジョン研究センター、慶應義塾大学AIメディカルセンター、エムスリー株式会社m3.com編集部が主催して開催します。
第10回は、講師にAMI株式会社代表取締役CEO/循環器内科医の小川晋平氏と東京大学医学部附属病院循環器内科助教の小寺聡氏をお迎えし、循環器領域におけるAIの利活用・開発の現状と課題についてお伺いし、臨床現場の課題解決に向けた今後について参加者の皆様とディスカッションをします。
小川晋平(おがわ・しんぺい)
AMI株式会社代表取締役CEO/循環器内科医
熊本大学医学部卒。開発中の超聴診器はNEDOの研究開発型ベンチャー支援事業にも2回採択されており第1回Healthcare venture Knotや第1回メドテックグランプリKOBEなど計5つのベンチャーピッチで最優秀賞を受賞している。各省庁からも高く評価されており、2017年の総務省のInno-vationに代表個人が選出。2018年九州経産局のヘルスケア産業づくり貢献大賞の大賞に選出。2019年10月には厚生労働省から将来有望なベンチャー企業に選出されて「JHVS2019 Venture Award」を受賞した。
小寺聡(こでら・さとし)
東京大学医学部附属病院循環器内科助教
2001年東京大学医学部医学科卒業。東大病院、国保旭中央病院、佐伯中央病院で循環器内科の臨床に従事。2015年に東京大学大学院公共健康医学専門職学位課程修了(生物統計学教室)。2016年より現職。日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医。AI研究で欧米・中国に日本が遅れをとっていることに危機感を感じ、独学でPythonなどプログラミング言語を習得し、循環器領域にAI研究に取り組んでいる。
江間有沙(えま・ありさ)
東京大学未来ビジョン研究センター特任講師/国立研究開発法人理化学研究所革新知能統合研究センター客員研究員
2012年東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士(学術)。京都大学白眉センター特定助教、東京大学教養学部附属教養教育高度化機構、同大学政策ビジョン研究センターを経て現職。日本ディープラーニング協会理事/公共政策委員会委員長、人工知能学会倫理委員会副委員長。人工知能の倫理やガバナンスについてを研究テーマとしている。著書に『AI社会の歩き方-人工知能とどう付き合うか』(化学同人)など。専門は科学技術社会論(STS)。
藤田卓仙(ふじた・たかのり)
世界経済フォーラム第四次産業革命日本センター ヘルスケア・データ政策プロジェクト長
2006年、東京大学医学部卒業。慶應義塾大学メディカルAIセンター、慶應義塾大学イノベーション推進本部とも兼任。医療政策学、医事法学、医療経済学、医療情報学の観点から、学際的な研究を行う。健康医療情報のプラットフォーム化と情報の利活用、大学医学部における産学官連携、地域包括ケアシステム・在宅医療における法政策、医療事故と専門職の責任、ヘルスケアにおける広告表示規制、医療等個人情報保護法制、医学領域における知的財産権などを研究テーマとしている。
東京大学未来ビジョン研究センター、慶應義塾大学メディカルAIセンター、エムスリー株式会社m3.com編集部が2019年11月30日に開催した医療×AIセミナーシリーズ第10回「循環器とAI」を開催した。講師にAMI株式会社代表取締役CEO/循環器内科医の小川晋平氏と東京大学医学部附属病院循環器内科助教の小寺聡氏をお迎えし、循環器領域におけるAIの利活用・開発の現状と課題についてお伺いし、臨床現場の課題解決に向けた今後について参加者の皆様とディスカッションをします。

最初に登壇したのはAMI株式会社代表取締役CEOで循環器内科医の小川晋平氏。同社が開発を進める「超聴診器」の研究開発の状況や、循環器の医師が手探りの状態からAI(人工知能)の研究に取り組むまでの実際の経験などについて話した。
もともと臨床医だった小川氏は、2015年11月に一人で起業した。社名のAMIは、「アキュート・メディカル・イノベーション」の略で、苦労しながらも右肩上がりに上がっていくという意気込みも込めている。医療機器を開発しているので大学発ベンチャーと思われることも多いが、机1つと自己資金だけで特許も製品も何もない状態から始まり、当初は勤務先の病院で研究をさせてもらっていたという。それが4年で社員は19人に増え、医療従事者やソフトウェアの開発者、ハードウェアの開発者、3Dエンジニアと連携し、全国に4カ所の拠点を置き、音のための本格的な防音室を備えた研究所も設置するまでになった。
自己資金だけで研究開発を進めていた最初の2年間をなんとか乗り越え、現在は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の支援やベンチャーキャピタルからの出資を受けている。国からの研究費の支援以外で会社の業績に応じて研究費を確保できるようにするために、株式会社にしたと小川氏はいう。そして複数の大学と臨床研究で連携し、当初の製品が何もなかった段階から、現在は最初の製品の薬事申請の準備をするところまで着々と成果を積み重ねており、来年度くらいには「超聴診器」の最初の製品を出すことを目指している。3回は死ぬとされる研究開発ベンチャーだが、資金調達などで2つの難関を乗り越えてきており、この先の最後の「ダーウィンの海」を越えていくための準備もしっかり進めていると語った。
聴診器にAIを組み合わせて心疾患の早期発見へ
小川氏が開発を進めている「超聴診器」は正式には「心疾患診断アシスト機能付遠隔医療対応聴診器」という。元々は心臓病を診ていた医師として、国内には推定患者が100万人はいるとされる大動脈狭窄症を早期発見することで、この病気で亡くなる人を少しでも減らしたいと思ったことが開発のきっかけだった。特に5年前、カテーテルを使った治療に関わり、開胸せずに済む負担が少ない新しい選択肢があるにもかかわらず、適切な治療にたどりつけていない人がたくさんいることに気付き、症状が出てからでは予後が悪いため、症状が出る前にどうやって早期発見するかが重要だと考えるようになったという。とはいえ、検査を受ける人全員にカテーテルや心エコーを使うのは現実的ではないため、聴診器を活用できないか、それも医師が耳で聞くのではなくAIも活用しながら、診断の支援を自動化できないかと研究に着手した。
聴診器は約200年前にフランスで発明されたが、その後ほとんど変化していない。50年前には現在とほぼ同じ形が完成され、30年ほど前に一部デジタル化された聴診器も出現したという程度の変化だ。ただ、音の解析だけでは限度があるため、心電も一緒に捉えて心筋活動電位が発生するタイミングに揃えて心音を重ね合わせて記録するプログラムを作り始めたという。とはいえ、久々に半田ごてを使ったが電子回路は作れず、論文を読み漁って協力してくれそうな人を探したという。同時に、それでもまずは自力でどこまでできるかを確認するためにも、音の専門家のアドバイスを受けてまずは音の解析環境を整えた。少し前であれば試作品を作るために何百万円もかかってしまったかもしれないが、今は3Dプリンターを使った樹脂製のものであれば数千円、金属製でも数十万円で作れるようになっている。協力者の力も借りながら、聴診器の小型化を進めたり電極の位置を見直したりと試行錯誤を繰り返して、今も超聴診器のプロトタイプをどんどん作っているという。
20ヘルツ以下の心音の世界へ
超聴診器の特長は大きく分けて4点あるという。まず1点目は、他の聴診器と比べて圧倒的に高いs/n比だという。小川氏自ら世界中の電子聴診器を集めて比較して確認したという。2点目は、膨大な臨床データに裏付けられているということだ。エコー技師など様々な分野の専門家集団を揃えて、日々実験を繰り返しながら、心音と心電の重ね方を検討しているという。また、3点目として、最適な結果が得られるようにソフトウェアも自社で開発している点を小川氏は挙げた。知財にも力を入れて研究開発を進めていると強調した。
そして最大の特長として、人の耳には聞こえない周波数帯の音まで解析できることを4点目として挙げた。これこそが超聴診器の「超」たる所以だという。超聴診器では音をフーリエ変換して視覚的に表示するため、聞こえない音についての提示も可能になっている。例えば虹を見たときに見えない赤外線や紫外線などの層があるように、音にも聞こえない領域があるという。そしてそうした聞こえない領域を聞くためには、新たな技術が必要で、それが超聴診器になる。人に聞こえるのは20ヘルツから2万ヘルツの間にある周波数の音だが、超聴診器は20ヘルツ以下の世界にも切り込む。小川氏によると、研究開発する上でこの領域を最も重要視しており、戦略的に特許を固めているところだという。
心音の活用に向けてデータの質を追求
医療とAIについて、小川氏は個人的な考えとしてビッグデータがやはり重要だと強調し、その上でデータの量と同じくらいデータの質も重要だという見解を示した。ハードとソフトのエンジニアが、臨床データを活用するという3つで研究開発を回しているという。いいデータでなければ掬い取れないものがあり、いいデータであっても分析ができなければ意味がない。そして循環器の領域では心電図やCTは完成した技術だが、心音は完成しているように見えてまだ開拓の余地があるとした。今までよりも1ヘルツでも周波数の低い音を読み取れるように、本当は成果を明らかにせずに10年ぐらいひっそりと研究を進めたいが、研究よりも社会実装が必要と考えて今から一気に製品化を目指すとの意気込みを語った。
遠隔医療にも「超聴診器」を活用へ
そして最後に、小川氏は超聴診器の遠隔医療への応用について話した。いい音を取れれば遠隔でも利用できるはずだと思っていたが、実際は通信機器やスピーカーなどを通すと音が変わって診断に必要な情報が落ちていってしまうという。そこで、音のデータを通信によって飛ばす前に、壊れないように可視化されたデータに変える方法を開発している。小川氏は現在も循環器の外来で患者を診ており、一部遠隔医療も取り入れているが、オンラインの聴診はほとんど実施されていないという。遠隔医療に関心がある自治体と連携しながら、超聴診器の活用先をさらに広げようとしている。4年前に一人で始めた時はなかなか理解されなかったのが、いよいよ技術を実現できる段階になり、理解者が増えてきたことを感慨深く振り返った。

続いて登壇したのは東京大学医学部附属病院循環器内科助教の小寺聡氏。虚血性心疾患の治療などに取り組む臨床医で、「機械音痴」でビデオの録画も苦手だが、AI研究を一から始めて半年間である程度のことができるようになってきたという自身の経験を紹介した。
AIと聞くと、なんだか難しそうで医療の現場に入ってくると「仕事を取られてしまうのではないか」という漠然とした不安を小寺氏も感じていたという。それが半年前に、同じ大学の工学部のAI研究の第一人者の松尾豊氏の講演を聴き、欧米や中国がAI研究を進める中で日本が遅れつつある状況を知ることになる。自分のような「機械音痴のオジサン」が頑張ったら少しは状況が変わるのではないか、循環器科でAI研究に取り組めば他の分野にも広がるかもしれない、と思ったのがAI研究に取り組むきっかけだったという。そして現在、胸部エックス線画像から心不全を診断支援するAIソフトの開発を進めて近く論文を投稿するところまで来た。企業との共同研究も3件検討するなど、開始から半年にしてはひとまずの進捗状況なのではないかと振り返った。
小寺氏は当初、プログラミングはせずに、マウス操作でAIを利用できるソニーの「Neural Network Console」の利用を試みた。ただ、途中でうまくいかなくなった時に何が起きているかが分からないため対策を取りにくく、結局プログラミング言語の勉強を始めることにした。ひたすら参考書のコードを写す「写経」のような作業を2カ⽉ほど続けたという。AIの分野では標準的に利用されているプログラミング言語「Python」をパソコンにインストールし、仮想環境を用意できるパッケージ「Anaconda」もインストールした。どこか物騒な名前(Pythonはニシキヘビ、Anacondaは大蛇)だと感じていたらパソコンがフリーズしてしまい、仕事用の大事なパソコンではない機器を使うべきとの教訓も得ながら、AIでは典型的な画像を分類するような練習問題はこなせるようになっていた。
書籍やオンライン講座で学ぶプログラミングの実践
コードを写していくと、次第に書かれていることの意味が知りたくなる。そこで入門の書籍を購入し、ディープラーニングの理論面や実践もそれぞれ別の教科書的な書籍で勉強しながら進めていったという。一方で、本だけでは分からない部分もあったため、小寺氏はオンライン学習サイトも活用した。ProgateやAidemyなど、正解のコードと自分が書いたものを比較できるものもあり、有料のコースも受講し、全部でAIのためのコードの勉強に数万円かけたのではないかと振り返る。実際のプログラミングで役立っているのは、グーグルの検索だという。コードを書いている時にエラーがあると、そのエラーメッセージをそのまま検索するとアドバイスが書かれているウェブサイトがあり、参考にしながら解決できることが多い。
そもそも医師がプログラミングを勉強する必要があるのだろうか。小寺氏は研究費を確保できるかどうか次第だとした。プログラマーに依頼する方法もあるが、AIの分野の盛り上がりを受けてプログラマーの人件費は上がってきている。資金がなければ、自力でやるだけで、そのための道具は揃ってきている。
自前チームで小さく始める
小寺氏も一人では挫折しそうだと感じたため、同じように興味を持っている人を集めてチームを作った。医師だけではなく学生もいる自主的なグループだが、こうしたグループを作る際に何が必要なのかを洗い出すために他の研究チームにヒアリングを実施した。研究費があるチーム、外からプログラミングの専門家を呼んでいるチームなど、すぐには参考にはしにくいチームが多い中で、まずは個人パソコンで自前の研究費でプログラミングを始めて、ある程度データが出せるようになってから企業の支援を受けるようになった東大のチームについて知った。最初は小さく立ち上げることも可能だと感じ、自分たちの施設のデータ、可能な範囲での高性能なパソコン、自前の研究費、そして自力でのプログラミングで研究に着手した。
最初に挑んだのが、胸部エックス線画像による心不全の診断に深層学習は有効かどうかの検証だった。肺の疾患に関する先行研究はあるが心不全は少なく、米国のサンプルデータを利用した。チームの学生メンバーがパソコンでプログラムを書き、心不全の予測精度を上げていくということを繰り返した。そして心臓が大きくなっている症例の画像を心不全と約9割の画像で正しく予測できるまでになったという。ここでも役立ったのがKaggleというオンラインで機械学習による解析を競い合うサイトで、一流プログラマーが自分たちの関心テーマに近い分野向けに書いたコードを利用できたという。今後はこうしたサイトを介して、医師もいい解析モデルをさらに作りやすくなるのではないかと小寺氏は見ている。
進むAIの「民主化」
最近の関心事として、AIの「民主化」への関心が高まっていることを小寺氏は紹介した。データサイエンティストらがプログラミング言語を使ってコードを書いて解析するような時代から、プログラムが不要で誰もがAIを使える時代への移行も近いという。データを入力すればあとはスタートボタンを押すだけで数百のモデルを自動的に試すようなプログラムも登場していて、今は高価でもいずれは広く普及する可能性がある。深層学習の論文検索回数はPubmedでも伸びていて、医療現場にAIが導入されるのも時間の問題だ。一方でAIはなんでもできるスーパーマンではない、と小寺氏は実際に一から研究をしてみた実感として強調した。現状ではデータのラベル付けなどが必要で、まずは過度に期待せずに人間にとって面倒なことを代わりにやってもらうのがいいのではないかと提案した。
AIの活用のためにはやはりデータが重要で、AI時代には石油に代わるものがデータだとされ、量も質も両方必要だとした。AI研究に力を入れる中国はデータの量があり、日本でも国を挙げてデータ収集を進めているが、まだ循環器の領域ではデータ収集もラベル付けも遅れているという。循環器系の検査に注力している日本の医療法人社団CVICもすでに2年前に中国のベンチャーと提携している状況だ。日本でAIの研究の活性化が必要であることを小寺氏は改めて強調した。
難易度は「エベレスト登頂」並みから「高尾山登山」並みへ
AI研究に実際に取り組んで困ったこととして、できることとやりたいことの間に大きなギャップがあることを挙げた。例えばチームで開発した心不全の予測プログラムも、心不全についてしか学習していないため、肺炎も併発しているような症例には対応できない。本当に臨床現場で使えるようなプログラムを開発するためには自力での研究開発は限界があるが、役に立つことを最初から目指してしまうと何もできなくなってしまうため、結局はできるところから一歩ずつ、コツコツと進めるしかないという。様々なパッケージソフトも揃っているため、最初はエベレスト登頂ぐらいに大変かと思っていたAI研究も、実践してみた実感としては富士山登頂だったと表現した。将来的には高尾山を登るような感覚で研究に取り組めるようになるのではないか、と期待を込めた。
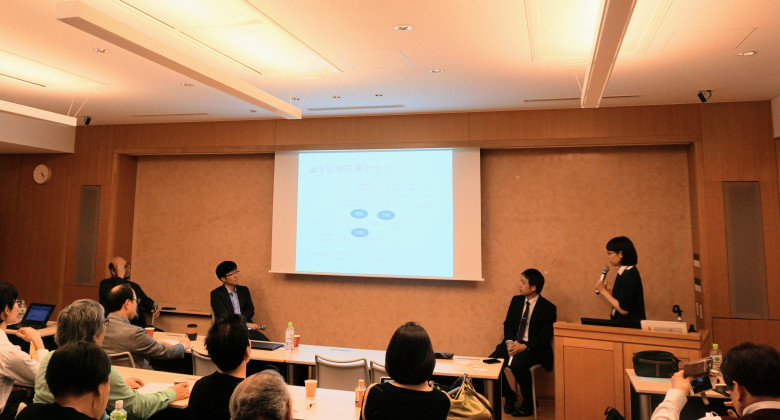
最後のパネルディスカッションではこれまでに登壇した「超聴診器」の研究開発を進めるAMI株式会社代表取締役CEOで循環器内科医の小川晋平氏、東京大学医学部附属病院循環器内科助教の小寺聡氏に加えて、東京大学未来ビジョン研究センター特任講師の江間有沙氏と慶應義塾大学メディカルAIセンターの藤田卓仙氏の2人がディスカッサントとして加わり、AI研究の実際について議論した。主な議論を以下に紹介する。
AI研究の様々なパス、実践者に聞く課題克服の鍵
AI研究はきっかけもゴールも、その間をつなぐ道筋も様々で、課題の克服の仕方がそれぞれの研究者やチームによって異なるという状況を江間氏が改めて示した。そしてAI研究を一から始めた登壇者に、課題克服の鍵や現状の課題について尋ねた。小川氏は一緒に研究開発を進める仲間を探し出すことが重要だとした。解析のためのソフトウェアも自力では作れなかったため、できるところまで作った未完成のものを専門家に見せて、「ここから先はできません」と助けを求めるなどして、現在のチームのメンバーにも出会えたという。その分、自身は経営者としてのスキルを磨くことに集中し、知財の戦略も考えて資金調達につなげ、チーム全体を強くすることができたと振り返る。自身の能力や強みを見極めることも必要だとした。
一方の小寺氏は、AI研究を始めた動機として、日本のAI研究を活性化するために一人でも参入者を増やしたいからだったと話し、課題を突破できるか分からないまま研究を進めてきたと振り返った。それでも学生を含めたチームのメンバーと一緒になって半年勉強してある程度のことができるようになった今、臨床研究をどう進めるべきか、次の手をどう打つべきかを検討していると話した。
研究者、大学、産業界、国… それぞれを活用する視点も重要
藤田氏は、何が特定臨床研究に該当するかはよく議論があるとし、大学での産学連携のサポート役がアドバイスをできる可能性があると話した。実際に藤田氏は大学でのAI研究のプロジェクトの立ち上げにも関わっていて、小川氏と小寺氏でも研究の進め方が異なるように、様々な道筋があると改めて指摘した。これまでも現場の医師の問題意識を出発点に、課題を克服するための技術を持っている人を集めて、さらには研究費を獲得するために知恵を働かせてきたという。最近はAI研究のツールが増えているため、AIを使うことのハードルは下がってきているものの、研究の裾野が広がって先行しているチームがあると公的な研究費の獲得のハードルが上がっているかもしれないとした。
きっかけも多様なAI研究では、どうゴールを設定するかも様々だ。小川氏は当初から医療革新を実現することがゴールだと言い続けてきたという。心疾患の治療をしたいと思ったのはきっかけの一つでしかなく、目指すのは意識して別のところにしているとした。医療では、例えば医師になることが目的になったり手段になったりするが、世の中にどう貢献できるかを考えて実現する方向に向かっていけばいいはずだという自身の考え方を話した。その中で、まず短期的なゴールの一つとして、AIによる診断支援の機能を持った医療機器を、治験を実施して世の中に出すことだとした。
小寺氏は、そもそも分野全体の発展のために始めたAI研究だったことから、最初のゴールは小さくても自分が研究することを意識したとした。だが、なかなか患者の役に立てるところまでたどり着けないということが実際に研究してみてあったという。例えば血管内超音波検査の場合、画像から症例が正常か異常かを推測するようなAIのためのプログラムは書ける。だが、臨床現場で実際に使えるようにするためには、血管の分岐やアーチファクトの種類など、AIに学習させなければならないことが数多くある。そのためには症例数が必要で、さらには企業の支援も欠かせなくなってくるという。ただ、企業との連携となると、ゴールは何か具体的な製品の開発になり、当初の目標からずれてきてしまうという難しさもあるとした。
「早期の事業化」と「将来の医療革新」のはざまで
会場からの質問にも登壇者2人は答えた。「超聴診器」の製品化を2年後に目指す小川氏には、医療機器ではなく誰もが簡単に利用できるようにスマートフォンのソフトにして事業化を先に進めるといいのではないか、との意見があった。これに対して小川氏は、超聴診器はハードとソフトの両方が重要であるとまずは答えた。そして事業として成立させることではなく、医療のイノベーションが本来の目標であるため、仮に資金が必要だとしても圧倒的なデータ量を取り込んだ上で世の医療機器として出したいということ、つまりは「目先の利益より、医師として正しいと思うことをする」という自身の考えの根幹を話した。実際、現在ベンチャーキャピタルからの出資は、こうした考えに賛同した上でのものだという。
AIを診断の支援に役立てようとする研究開発は多くあるが、新しい治療法の開発にも繋がるのか、研究開発の現状を尋ねる質問もあった。これに対して小寺氏は、例えばがんの領域では遺伝子情報もモデルに入れて症例の原因を予測して治療を選択するような取り組みもあると具体例を示した。医療の分野では、患者への説明も重要なため、説明可能なAIプログラムが重要になる。そのためには、説明できるAIのプログラムを開発する方法と、AIによって重要と認識された因子を研究することで病気のメカニズムを明らかにしてAIを説明可能にする方法があると話し、工学と医療の両方の側面から研究開発が進んでいる現状を紹介した。